

日本最古のひきこもり?

こんにちは。プロフェッショナル心理カウンセラーの金崎です。
今日は少し変わった視点から、「引きこもり」について考えてみたいと思います。
「日本最古の引きこもりって誰だと思いますか?」
こう聞かれたら、あなたは誰を思い浮かべますか?
歴史の中の隠者たち、例えば『方丈記』を書いた鴨長明や、『徒然草』の吉田兼好を思い浮かべる人もいるかもしれません。彼らは俗世を離れて山にこもり、静かな生活を選びました。
でも、実はもっと古い「引きこもり」が、日本神話の中に描かれているんです。
そう、それは──
太陽の女神、天照大神(あまてらすおおみかみ)。
■ 天照大神は、なぜ「引きこもった」のか?
神話によると、天照大神は弟の須佐之男命(すさのおのみこと)の乱暴な振る舞いに心を痛め、ついには「天岩戸(あまのいわと)」という洞窟に閉じこもってしまいます。
太陽の女神が姿を消すと、世界は真っ暗になります。作物は育たず、祭りも止まり、人々の営みは止まりました。
この状況に困り果てた八百万(やおよろず)の神々は、岩戸の前で相談会を開き、なんとか天照大神を外に出そうと、知恵を出し合います。
結果的に、アメノウズメの踊りや神々の笑い声によって、天照大神は「何が起きているの?」と気になって岩戸から顔を出し、最終的には外に戻ってくることになります。
■ この神話、現代の「引きこもり」と重なりませんか?
現代では、「引きこもり」という言葉には、社会的な困難やストレス、心の傷などが背景にあります。
1、職場や学校での人間関係に疲れた
2、家庭内での葛藤がつらい
3、自分に自信が持てない
4、外の世界に出ることに恐怖がある
こういった理由から、人は自分の殻に閉じこもりたくなるのです。
天照大神もまた、信頼していた弟の乱暴によって、心が大きく傷ついた。その反応としての「岩戸隠れ」は、まさに心の安全を確保するための自己防衛反応だったのではないでしょうか。
■ 無理に引き出さない。「待つ」「信じる」「楽しさを届ける」
注目したいのは、神々の対応です。
誰も天照大神を責めたり、無理に引き出そうとはしませんでした。
彼らがしたのは、「楽しそうな空気をつくる」こと。
踊り、笑い声をあげ、安心できる空気を岩戸の外に届けたのです。
これは、現代の引きこもり支援にも通じる、大切な姿勢です。
▼ 現代の引きこもり支援の基本姿勢
無理に外へ出さない
本人のタイミングを尊重する
安心できる関係性を築く
小さな楽しさや希望を届ける
社会の方が寄り添う・変わる
天岩戸神話のように、誰かが戻ってくるには、その人が「少し顔を出してみようかな」と思えるきっかけと、「戻ってもいいんだ」と思える安心感が必要です。
■ なぜ私たちは「引きこもり」に冷たくなってしまうのか
現代社会では、「働いていること」「学校に行くこと」「人と関わること」が当たり前で、正しいという価値観が根強くあります。
そのため、引きこもる人に対して
1、「なまけている」
2、「甘えている」
3、「逃げているだけ」
というような偏見が向けられることも少なくありません。
しかし、天照大神はどうでしょう?
神々は決して「何やってるんだ、早く出てこい」とは言いませんでした。
この神話は、「引きこもることは、悪ではない」というメッセージを、実は遠い昔から私たちに伝えてくれているのかもしれません。
■ 「出てくる力」は、誰の中にもある
もうひとつ大切なのは、「出てくる力」は、引きこもった人自身の中にあるということです。
神々がどれだけ騒いでも、天照大神が自分から「顔を出そう」としなければ、岩戸は開かれなかったでしょう。
現代のカウンセリングでも、無理やり誰かを変えようとするのではなく、「変わりたい」「動いてみたい」というその人自身の思いを、そっと支えることが大切です。
■ 最後に:古代神話が、私たちにくれるもの
天岩戸神話は、たったひとつの「神話の物語」でありながら、現代の心の問題にも大きな示唆を与えてくれます。
1、傷ついた心が隠れることは、人間として自然なこと
2、無理に引きずり出すのではなく、寄り添うこと
3、出てくる力は、その人の中にある
これは、心理カウンセラーとして日々クライエントと向き合う中で、私が何度も感じてきたことでもあります。
もし、あなたの周りに引きこもっている誰かがいたら、
または、あなた自身が今、心の岩戸の奥にいるように感じているのなら、
どうか覚えていてください。
あなたは、ただ休んでいるだけ。戻るタイミングは、あなた自身が決めていい。
神々は、外で待ち、信じ、そしてあなたが顔を出すそのときを、笑顔で迎えてくれるでしょう。


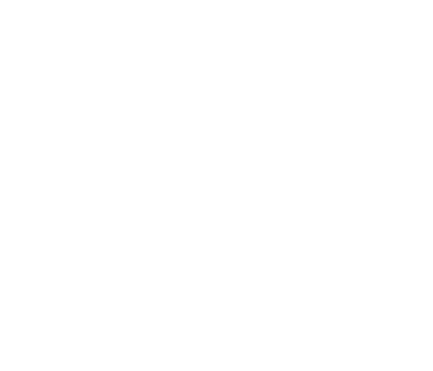 体験講座
体験講座