

昭和 VS 平成 VS 令和

昭和・平成・令和の心理カウンセリングと不登校
はじめに
「不登校は昔にはなかった」と言う方もいます。ですが、実際にはどの時代にも「学校に行けない子ども」は存在しました。ただ、その受け止め方や周囲の反応、そして支援の仕方が時代によって大きく異なっていたのです。
昭和の子どもは「怠けている」と叱られ、平成の子どもは「心のケアを」と支援を受け始め、令和の子どもは「多様な学び方」が認められるようになりました。心理カウンセリングもまた、この流れの中で役割を変えてきました。
ここでは、昭和・平成・令和という三つの時代を振り返りながら、不登校と心理カウンセリングの関わりをわかりやすく整理していきます。親御さんが「今、どう子どもと向き合えばいいのか」を考えるヒントになればと思います。
昭和の子どもと不登校
「学校は絶対行くもの」という常識
昭和の時代、学校は「義務」であり「絶対に行くもの」でした。親も先生も「学校に行かない」という選択肢を考えることはほとんどありませんでした。
たとえば、私が以前お話を伺った60代の女性はこう語っていました。
「私の息子が小学生の頃、急に『学校に行きたくない』と言ったことがありました。でも私も夫も、『何を言ってるの、行きなさい!』と無理やり玄関から送り出していました。当時はそれが当たり前だったんです。学校を休ませるなんて、恥ずかしくて近所に言えなかった。」
昭和の価値観では、「我慢」「努力」「根性」が美徳とされました。不登校は「甘え」「怠け」とされ、親は子どもを叱咤し、学校に行かせようと必死になったのです。
カウンセリングの影の存在
心理カウンセリングは一部の医療現場や教育現場にはありましたが、一般的には知られていませんでした。子どもが不登校になると、まずは親や教師がなんとかしようとし、それでもダメなら「精神科」へ行くしかない、という状況。
「カウンセリング」という言葉自体が、まだ多くの家庭には届いていなかったのです。
そのため、不登校の子どもも親も孤立しやすく、周囲に相談できずに家庭内で抱え込み、苦しむケースが多く見られました。
平成の子どもと不登校
社会の変化と「心のケア」への注目
平成は、バブル崩壊・リストラ・震災など不安が続いた時代でした。この中で「心の問題」が社会的なテーマとして注目され始めました。
とくに大きな変化は、1995年から始まったスクールカウンセラー制度です。学校に心理の専門家が配置され、不登校やいじめ問題に対応する体制が整っていきました。
この頃から、親も「子どもが学校に行けないのは、心の問題が背景にあるのかもしれない」と考えられるようになり、不登校は「家庭の恥」から「社会が一緒に考えるべき課題」へと移り変わっていきました。
親御さんの体験談
40代のお母さんが、こう振り返っていました。
「平成の後半に娘が不登校になりました。当時はちょうどスクールカウンセラーが学校に来ていて、私も相談に乗ってもらいました。正直、『カウンセリングなんて意味あるの?』と思っていたのですが、娘が『あの先生と話すと落ち着く』と言っているのを見て、初めて大切さを実感しました。」
カウンセリングの方向性
平成のカウンセリングは、認知行動療法など「考え方の癖」を直す実践的なアプローチが取り入れられるようになりました。しかし、当時は「どうにかして学校に戻す」ことがゴールに置かれることが多く、子どもにとってはプレッシャーになる場合もありました。
「不登校=問題行動」という認識はまだ根強く、親も「どうやって学校に戻すか」に必死でした。
令和の子どもと不登校
「不登校=多様な学びの一つ」
令和になり、不登校のとらえ方は大きく変化しました。文部科学省も「不登校を問題行動ととらえるのではなく、子どもの成長に必要な時間」と位置づけを変えています。
フリースクールやオンライン学習、ホームスクーリングなど、学校以外の選択肢が増え、子ども自身が「安心して学べる場所」を選べるようになりつつあります。
親子のカウンセリング
令和のカウンセリングは、子どもだけでなく親へのサポートも重視されるようになっています。
「子どもをどう変えるか」ではなく「親がどう理解し、寄り添うか」を一緒に考えるのです。
あるお母さんは、カウンセリングを受けた後にこう言いました。
「私はずっと、息子を『どうやって学校に戻すか』しか考えていませんでした。でもカウンセラーの先生に『まずは安心できる家庭を作ることが大事です』と言われて、肩の荷が下りたんです。息子も少しずつ笑顔を取り戻しました。」
子どもの自己理解を支える
令和のカウンセリングは、「学校復帰」だけが目的ではありません。子どもが自分のペースで自己理解を深め、「どう生きたいか」を考える時間を支えます。
その結果として学校に戻る子もいれば、別の道を選ぶ子もいます。大事なのは、子どもが「自分らしい生き方」を見つけられることです。
親御さんへのメッセージ
昭和では「我慢させる」
平成では「学校へ戻す」
令和では「子どもの人生を支える」
——このように、不登校への向き合い方は大きく変化してきました。
親御さんに伝えたいのは、次の三つです。
不登校は失敗ではなく、成長のプロセス
子どもが立ち止まることは、心が育つために必要な時間でもあります。親も支援を受けていい
子どもに寄り添うためには、親自身が安心できる居場所を持つことが大切です。カウンセリングは親のためにもあります。学校復帰だけがゴールではない
大切なのは「どんな道を選んでも生きていける力」を育むこと。学校に戻ることよりも、子どもが自分らしさを取り戻すことが一番の目的です。
おわりに
不登校は「現代だけの問題」ではなく、どの時代にも存在してきました。ただ、時代とともに心理カウンセリングの役割も変化し、今は「子どもの多様な生き方を支えるための支援」として位置づけられています。
親御さんが「うちの子は大丈夫だろうか」と不安になるのは当然です。でも、不登校は子どもが成長するための大切な時間でもあります。心理カウンセリングは、その時間を子どもと親が安心して過ごせるようにサポートするものです。
どうか一人で抱え込まず、安心して頼れる場を見つけてください。
そして、子どもと一緒に「今をどう生きるか」を考えていきましょう。

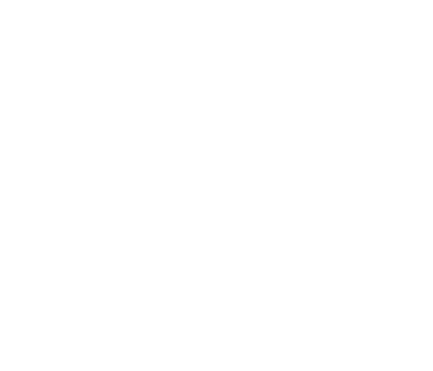 体験講座
体験講座