

心の働きとは

思考・感情・行動の仕組み ― 心理カウンセラーが解き明かす“
心が動くメカニズム”
心に寄り添うカウンセラーを育てる学校 TKN心理サロン
はじめに ― 「心の仕組み」を知ることがカウンセリングの第一歩
私たち心理カウンセラーが、日々の面談で最も大切にしていること。
それは「クライエントの思考・感情・行動のつながりを丁寧に読み解く」ことです。
人は出来事そのものに反応しているのではなく、自分の思考(考え方)によって感情が生まれ、その感情が行動を動かすという流れの中で生きています。
この仕組みを理解し、クライエント自身がそれに“気づく”瞬間、心は自然と回復へ向かいます。
TKN心理サロンでは、この「心の構造理解」を、カウンセリング実践と理論の両面から学びます。
今回は、その中核をなす「思考・感情・行動の関係」について、心理カウンセラー的視点で解説していきましょう。
第1章:思考 ― 感情を生み出す“内なる言葉”
思考とは、出来事に対して「自分がどう意味づけをしているか」という内的な言語化プロセスです。
カウンセリングでは、同じ出来事でも人によって感情がまったく異なる理由を、この「思考の違い」に求めます。
たとえば、同じ「上司に注意された」という出来事でも——
1、Aさん:「また怒られた。自分はダメだ」→悲しみ・自己否定
2、Bさん:「教えてもらえて助かった」→安心・感謝
この違いは、出来事そのものではなく、思考のフィルターの違いです。
心理学では、こうした自動的に浮かぶ思考を「自動思考(Automatic Thought)」と呼びます。
カウンセラーは、クライエントの言葉の中からこの自動思考を丁寧に拾い上げ、無意識に働いている“意味づけのクセ”を見つめていきます。
TKN心理サロンの養成講座では、こうした「思考の認知プロセス」をリフレーミングやABCモデル(Albert Ellis)を通して体系的に学びます。
カウンセリングで大切なのは、「思考を変えさせること」ではなく、「思考に気づかせること」。
気づきこそが自己理解の扉を開く鍵となります。
第2章:感情 ― 思考の影にある“心の反応”
感情は、思考に続いて生じる「体の反応」とも言えます。
悲しみ、怒り、不安、喜びなど、感情は人間の内なるエネルギーの流れです。
カウンセリングでよくあるケースとして、
「感情を感じたくない」「泣くのが恥ずかしい」「怒りを出したら嫌われる」
といった“感情の抑圧”があります。
しかし、感情を抑えることは、心の自然な動きを止めてしまうこと。
思考が感情をコントロールしようとするほど、心の中では葛藤が起きます。
心理カウンセラーの役割は、クライエントが安心して感情を感じられるよう**安全な場(セーフプレイス)**を提供することです。
そして、「どんな感情もあなたの中で生まれる自然なエネルギー」であることを理解してもらいます。
感情を「分析」ではなく「体験」として扱う。
それがTKN心理サロンのカウンセリング教育の特徴です。
第3章:行動 ― 感情が現実を動かす“結果の表現”
行動は、思考と感情が形となって表れる部分です。
しかし多くのクライエントは、「行動できない自分」を責めてしまいます。
「もっと頑張らないと」「変わらなきゃ」
——その“思考”自体が、プレッシャーや不安という“感情”を生み、結果的に行動を止めてしまうのです。
心理カウンセリングでは、行動の変化を目標ではなく結果と見なします。
行動は、心の内的プロセスが整ったときに自然に起こるもの。
無理に変えようとせず、感情と思考を理解しながら“自然な行動”を育てていきます。
TKN心理サロンでは、行動変容理論(トランスセオレティカルモデル)やブリーフセラピーの考え方を取り入れ、
「小さな行動変化」が自己効力感(self-efficacy)を育てるプロセスを実践的に学びます。
第4章:思考・感情・行動の三角形 ― カウンセラーが見る「心の構造」
カウンセラーは、クライエントの語る内容を「思考」「感情」「行動」の三角形モデルで整理します。
たとえば——
1、思考が硬直すると → 感情が抑えられ、行動が止まる
2、感情が爆発すると → 思考が混乱し、衝動的な行動になる
3、行動が過剰になると → 感情に気づけず、思考が空回りする
カウンセラーはこの三角形のバランスと流れを見立てながら、面談を進めます。
TKN心理サロンでは、ロジャースの「自己一致」概念を軸に、
この三角形が整う=**自己との調和(congruence)**が回復していくプロセスを重視しています。
第5章:カウンセラーが行う“心の翻訳作業”
実際の面談では、クライエントの言葉の背後にある思考や感情を「翻訳」していく作業を行います。
たとえば、
「私は頑張らなきゃダメなんです」という言葉の裏には、
「頑張らないと愛されない」という深い思考、
「認められたい」という感情が隠れています。
このように、カウンセラーは“言葉の下にある意味”を丁寧に掘り下げます。
それはクライエントにとって、自分でも気づかなかった“心の地図”を描き直す作業です。
TKN心理サロンの授業では、「ロールプレイ」「逐語検討」「ケーススタディ」を通して、
この“翻訳力”を体得的に学びます。
テクニックではなく、**人の心に共鳴する力(共感的理解)**を育てることが目的です。
第6章:理論から見る心の連動 ― 認知行動療法と人間性心理学の融合
TKN心理サロンでは、理論を単に知識として学ぶのではなく、
「体験を通して理解する」ことを重視しています。
思考・感情・行動の関係は、心理学の複数の理論で説明されています。
● 認知行動療法(CBT)
思考(認知)を修正することで、感情や行動の変化を促す。
→ 心理教育的なアプローチとして効果的。
● 来談者中心療法(ロジャース)
人は受容と共感の中で、自ら気づき・変化していく力を持つ。
→ 思考を変える前に、“感情の安全”を整える。
TKN心理サロンでは、両者を統合し、
「理性と感情」「理解と体験」をバランスよく扱う“実践的カウンセリング”を育てています。
第7章:思考・感情・行動を整える ― カウンセラーが使う実践的ワーク
🌿1. ABCモデルワーク
A(出来事)→B(思考)→C(感情・行動)を紙に書き出し、
「自分はどう意味づけていたか」を客観的に整理します。
🌿2. 感情の言語化ワーク
「怒りの下にある悲しみ」「不安の下にある願い」を探る。
感情を分解し、自己理解を深めるプロセス。
🌿3. 小さな行動実験
「今日は5分だけ自分を褒めてみる」など、無理のない変化を試す。
成功体験が自己効力感を育てる。
これらはTKN心理サロンの実習授業でも扱うワークです。
カウンセラー自身が体験することで、理論が“自分の血肉”になります。
第8章:自己理解から他者理解へ ― カウンセラーとして成長する道
「思考・感情・行動の仕組み」を理解することは、他者を理解する前に、まず自分を理解することにつながります。
カウンセラー養成の過程では、
「私はなぜこの反応をするのか」「どうして同じパターンを繰り返すのか」
という“自己洞察”が不可欠です。
TKN心理サロンでは、理論・実習・セルフワークを通して、
カウンセラー自身の“心の成長”をサポートします。
思考・感情・行動を整える力は、カウンセリングのテクニックではなく、
**人としての在り方(being)**そのものです。
おわりに ― 「心はつながりの中で整う」
思考が感情を生み、感情が行動を動かし、行動がまた思考を変えていく。
この循環の中に、人の成長と癒しがあります。
TKN心理サロンのカウンセリング教育は、
この心の流れを理解し、寄り添い、共に歩む人を育てることを目的としています。
心の仕組みを学ぶことは、誰かを助ける技術ではなく、
自分と他者の「心のつながり」を深める学びです。
🌸 TKN心理サロン
大阪で30年以上にわたり、心理カウンセラー養成と心の教育を行う専門機関。
来談者中心療法・ゲシュタルト療法・認知行動療法を統合し、
「心に寄り添うカウンセラー」を育成しています。

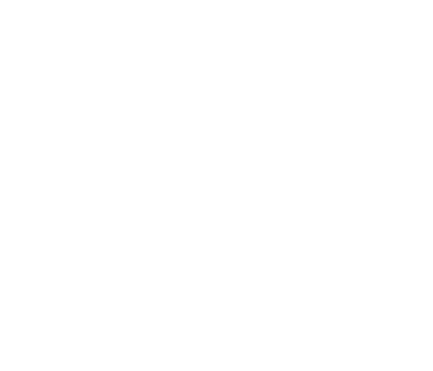 体験講座
体験講座