

共感の難しさとは

寄り添いと共感の違い 〜カウンセラーが伝えたい本当の「理解」とは〜
はじめに──「寄り添う」って、どういうこと?
カウンセリングの現場で最もよく耳にする言葉のひとつが、「寄り添う」です。
「クライエントに寄り添う」「気持ちに寄り添う」「痛みに寄り添う」──。
けれど、いざ自分が寄り添おうとすると、どこか難しさを感じる方も多いのではないでしょうか。
一方で「共感」という言葉も、カウンセリングにおける重要なキーワードです。
しかし、「寄り添う」と「共感する」は同じではありません。
むしろ、この二つを混同してしまうと、カウンセリングが「一緒に沈む関係」になってしまうこともあります。
TKN心理サロンでは、カウンセラーを目指す方々に「寄り添い」と「共感」の違いを丁寧に学んでいただきます。
なぜなら、ここを理解することが、“人を支える力”の本質だからです。
第1章 「寄り添い」とは何か
「寄り添う」という言葉は、日常的にもよく使われます。
たとえば、悲しんでいる友人に「寄り添いたい」と言ったり、家族に「寄り添う姿勢」を大切にしたいと話したり。
では、心理的に「寄り添う」とは、どんな状態を指すのでしょうか。
1.1 相手の世界に「足を踏み入れる」姿勢
寄り添いとは、相手の感じている世界の中に、そっと足を踏み入れることです。
相手の痛みや悲しみ、怒りや孤独といった“その人の内側の世界”を尊重し、「あなたがそう感じているんですね」と受け止める。
それが寄り添いの出発点です。
寄り添うとは、決して「慰める」ことではありません。
また「励ます」ことでもありません。
ただ、クライエントの感じている現実に対して、「あなたの感じていることには意味があります」と存在を認めること。
それが「寄り添う」という行為の根底にあるものです。
1.2 カウンセラーの“静かな受容”
寄り添うためには、カウンセラーの内側に“静かな受容”が必要です。
たとえば、クライエントが「もう生きていたくない」と口にしたとき、私たちはどう反応するでしょうか。
「そんなこと言わないで」「あなたには価値があるよ」と励まそうとする人もいるでしょう。
けれど、その言葉は時に、クライエントの気持ちを否定してしまうこともあります。
寄り添うとは、「あなたはそう感じているのですね」と、そのまま受け止めること。
自分の価値観を挟まず、相手の“今ここ”を尊重することなのです。
第2章 「共感」とは何か
一方で「共感」とは、相手の感情を理解し、それを“感じ取る”ことです。
心理学的には、共感(empathy)は「相手の内的世界を、自分の内側で再現する能力」と言われます。
2.1 感情の理解と体験の共有
たとえば、クライエントが「会社で孤立して苦しい」と話したとき、
カウンセラーが「それは寂しいですね。誰にも分かってもらえないように感じるんですね」と応じる。
これは、共感の応答です。
共感とは、相手の感情を“正確に理解し、感じ取り、言葉で返す”プロセスです。
つまり、単なる「同情」ではありません。
「私もそんな経験がある」と自分の体験を語ることでもありません。
共感とは、“相手の立場に立ち、相手の感じている世界を感じる”ことなのです。
2.2 ロジャースが示した「共感的理解」
カール・ロジャースは、「真の共感的理解」をカウンセリングの中心条件としました。
彼は共感をこう定義しています。
「相手の内的世界を、まるで自分のものであるかのように感じ取るが、
決してその“まま”に溺れてしまわないこと。」
つまり、クライエントの感情を感じながらも、そこに飲み込まれないこと。
冷静さと温かさを両立させた理解の姿勢が、共感の本質なのです。
第3章 「寄り添い」と「共感」はどう違うのか
ここまで読むと、「寄り添い」と「共感」は似ているようで、微妙に違うことがわかります
寄り添いは“関係のぬくもり”を生み、共感は“理解の精度”を高めます。
両方があって初めて、カウンセリングは安心と変化をもたらすのです。
第4章 寄り添いすぎる危険
カウンセラーを志す人の中には、「寄り添おう」とするあまり、クライエントの感情に巻き込まれてしまう人も少なくありません。
涙を一緒に流し、怒りに共鳴し、相手と“同化”してしまう。
これは一見、優しさのように見えますが、実はクライエントを支える力を失わせてしまう行為です。
寄り添いとは「共に感じる」ことではなく、「感じている相手のそばに在る」こと。
そこには、必ず一定の“距離”が必要です。
この距離こそが、カウンセラーの“安全基地”としての力になります。
第5章 共感が深まると、寄り添いは自然に生まれる
では、寄り添いと共感のどちらを優先すべきなのでしょうか。
答えは「共感を深めることで、自然と寄り添いが生まれる」です。
共感とは、相手の気持ちを正確に理解する知的なプロセス。
寄り添いとは、その理解に温度を加える情緒的なプロセス。
カウンセリングの中では、まず“共感的理解”を通して相手の世界を理解し、
その理解を“温かく包む”ことで寄り添いが完成します。
第6章 実践での使い分け──ロールプレイで考える
クライエント:
「仕事がうまくいかなくて…もうダメかもしれません。」
A:寄り添い的応答
「そう感じるほど、つらい時間が続いているんですね。
今、あなたがそう思うのも無理はありません。」
→ 受け止めと共感の間に“安心”を生む。
B:共感的応答
「ダメだと思う気持ちの裏には、“なんとかしたい”という思いもあるようですね。」
→ 相手の感情の中にある“気づき”を促す。
寄り添いは「安全な場」をつくり、共感は「自己理解」を深める。
この二つを行き来しながら、カウンセリングは進んでいくのです。
第7章 寄り添いと共感のバランスが、関係を育てる
TKN心理サロンのカウンセラー養成講座では、「寄り添いと共感のバランス」を特に大切にしています。
どちらか一方に偏ると、関係は不安定になります。
1、寄り添いだけでは、共に沈み込み、変化が起きにくい。
2、共感だけでは、冷たく、心が通いにくい。
寄り添いは「心のぬくもり」、共感は「理解の精度」。
この二つが重なり合うとき、クライエントは「自分は理解されている」と深く感じ、心が癒されていくのです。
第8章 寄り添う力を育てるために
寄り添うために必要なのは、“自分の心を整える力”です。
他人の痛みに触れるには、まず自分の心が安定していることが前提となります。
8.1 自分の感情に気づく練習
「私は今、どんな気持ちでいるのか?」
この問いを日々、自分に投げかけることで、他者の感情にも敏感になります。
8.2 評価を手放す
「良い・悪い」「正しい・間違っている」と判断する前に、「そう感じているんだな」と受け止める練習を。
8.3 沈黙を恐れない
寄り添いとは、言葉ではなく“存在”のコミュニケーション。
沈黙の中で共にいる時間が、最も深い寄り添いを生むこともあります。
第9章 TKN心理サロンで学ぶ「寄り添いの実践」
TKN心理サロンのカウンセラー養成講座では、理論だけでなく「体感」を通じて寄り添いを学びます。
ロールプレイやグループワークを通して、
「相手の気持ちをどう受け止めるか」「どこまで関わるか」など、実践的に身につけていきます。
寄り添いとは、技術ではなく“姿勢”です。
しかし、その姿勢は練習によって磨かれていきます。
多くの受講生が「自分の人間関係が変わった」「家族との会話が楽になった」と語るのは、
この“寄り添いの力”を身につけたからなのです。
第10章 まとめ──寄り添いと共感の融合が、癒しを生む
寄り添いと共感。
どちらも人の心を支える大切な柱です。
寄り添いは「あなたがここにいることを認めています」というメッセージ。
共感は「あなたの気持ちを理解しています」というメッセージ。
この二つがひとつになるとき、カウンセリングの場には“安心と希望”が生まれます。
それが、TKN心理サロンが大切にしている「人間理解の原点」です。
終わりに──“共に在る”ということ
寄り添いとは、相手を変えることではありません。
ただ、“共に在る”ということ。
人が本当に変わっていくのは、理解され、受け止められたと感じたときです。
カウンセラーとして、そして一人の人間として──
誰かの痛みを「分かろう」とし、「そのまま受け止めよう」とする。
その姿勢こそが、寄り添いと共感をつなぐ“癒しの架け橋”なのです。

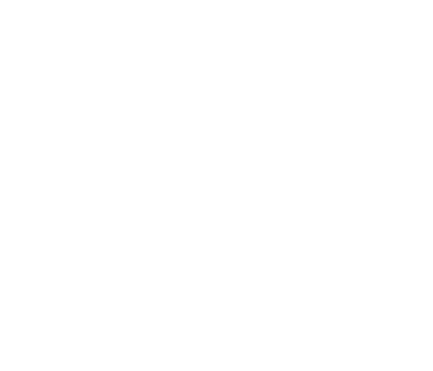 体験講座
体験講座