

エリクソンの発達心理学とは

エリクソンの発達心理学の重要性
― 人の成長を支える「心の発達段階」を学ぶ意味 ―
はじめに:なぜ今、エリクソン心理学が注目されるのか
心理カウンセリングの現場では、「今、この人はどのような発達課題の段階にいるのか?」という視点がとても重要になります。
クライエントが抱える悩みの根底には、過去に十分に満たされなかった心理的課題が隠れていることが多く、それが現在の人間関係や自己イメージ、選択の仕方に影響を及ぼしているからです。
エリク・H・エリクソン(Erik H. Erikson)は、人の一生を通して心がどのように発達していくのかを体系的に示した心理学者です。
彼の「発達心理学」は、単なる年齢の理論ではなく、「人生をどう生きるか」「自分をどう理解するか」に深く関わる学問であり、心理カウンセラーにとって欠かせない基礎理論です。
TKN心理サロンでは、カウンセラー養成の中でこのエリクソン理論を非常に重視しています。
それは、カウンセリングの基本が「その人の今の心の段階を理解し、寄り添うこと」にあるからです。
エリクソンとはどんな心理学者か
エリクソンは1902年にドイツで生まれ、後にアメリカに渡った心理学者です。
彼はフロイトの精神分析理論を基盤としつつも、より「社会的」「文化的」な視点を加えました。
つまり、人の成長は単に内面的な無意識の力だけでなく、「周囲の人々との関係性」「社会との関わり」の中で形成されていくと考えたのです。
この点が、エリクソンを単なる精神分析家ではなく、「人間発達の心理学者」として評価させた理由です。
エリクソンの提唱した「8つの発達段階」
エリクソンは、人の一生を8つの発達段階に分け、それぞれに「心理社会的危機(psychosocial crisis)」があるとしました。
それは「課題」とも言えるもので、うまく乗り越えることで次の段階へと成長していきます。
| 段階 | 年齢期 | 発達課題(危機) | 成長すると得られる力 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 乳児期(0~1歳) | 基本的信頼 vs 不信 | 希望(Hope) |
| 第2段階 | 幼児前期(1~3歳) | 自律性 vs 恥・疑惑 | 意思(Will) |
| 第3段階 | 幼児後期(3~6歳) | 主導性 vs 罪悪感 | 目的(Purpose) |
| 第4段階 | 学童期(6~12歳) | 勤勉性 vs 劣等感 | 有能感(Competence) |
| 第5段階 | 青年期(12~20歳) | 同一性 vs 役割混乱 | 忠誠(Fidelity) |
| 第6段階 | 成人初期(20~40歳) | 親密性 vs 孤立 | 愛(Love) |
| 第7段階 | 壮年期(40~65歳) | 生産性 vs 停滞 | 世話(Care) |
| 第8段階 | 老年期(65歳~) | 統合 vs 絶望 | 英知(Wisdom) |
発達段階を「カウンセリング」にどう生かすか
心理カウンセリングでは、クライエントが抱える問題を「表面的な悩み」としてだけでなく、「未完の発達課題」として見立てることが大切です。
たとえば——
1、「人に頼れない」「信じられない」という悩みの背景には、第1段階の「基本的信頼」の課題が関係しているかもしれません。
2、「自分を責めてばかり」「何かを始めるのが怖い」という人は、第3段階の「主導性 vs 罪悪感」でつまずいている可能性があります。
3、「自分が何者か分からない」「将来が見えない」という青年期の葛藤は、第5段階の「同一性 vs 役割混乱」のテーマです。
このように、エリクソンの発達理論を理解していることで、カウンセラーはクライエントの人生の文脈を丁寧に読み解くことができるのです。
人は「年齢」ではなく「心の段階」で生きている
興味深いのは、エリクソンの発達段階が「年齢に縛られない」という点です。
ある課題が未完のままだと、成人してもその段階に留まることがあります。
たとえば、40歳のクライエントが「人に頼るのが怖い」と感じているなら、それは乳児期の「基本的信頼」が十分に形成されていない可能性があります。
逆に、60歳を超えてから「ようやく自分を受け入れられた」と語る人もいます。
それは、老年期における「統合」の段階を、自分らしい形で迎えている証拠です。
TKN心理サロンでは、この「年齢ではなく心の段階を見る」という視点をとても大切にしています。
クライエントの年齢ではなく、「今どんな課題に取り組んでいるのか」「どんな気持ちで生きているのか」を理解する。
そこから本当の支援が始まります。
発達段階と「生育歴」の関係
カウンセリングでは、生育歴(幼少期からの家庭環境)を丁寧に聞き取ります。
これは単なる情報収集ではなく、「どの発達段階で何が起きたか」を知るためです。
たとえば——
1、親が忙しく、スキンシップが少なかった → 基本的信頼の不足
2、厳しく叱られて育った → 自律性や主導性の抑圧
3、成績や成果で評価された → 勤勉性は育つが、自己肯定感が低下
4、思春期に親や社会との対立を避けた → 同一性の形成が曖昧
このように、生育歴を「発達課題」というフィルターを通して見直すことで、クライエントが「なぜ今、同じパターンを繰り返しているのか」が明らかになります。
「未完の課題」を癒やすカウンセリング
エリクソンの理論を土台にしたカウンセリングでは、「過去をやり直す」ことではなく、「今の自分が過去の自分を理解し、癒す」ことを目指します。
TKN心理サロンのカウンセリングでも、この視点を大切にしています。
クライエントが安全な関係性の中で、過去の体験を語り直し、「あの時の自分に寄り添う」ことができたとき、未完だった発達課題が静かに完了していきます。
それは、まさに「心の成長」が今この瞬間にも起きているということです。
エリクソン理論と「自己理解」
発達心理学は、単に他者を理解するためだけのものではありません。
カウンセラー自身が「自分の人生をどう歩んできたか」を振り返る手がかりにもなります。
「私はどの段階で何を学び、どこに課題を感じているのか」
「今の私に必要な成長とは何か」
こうした問いを通じて、カウンセラー自身の人間理解が深まり、クライエントに対する共感もより豊かになります。
TKN心理サロンでは、自己理解のためにエリクソンの発達理論を用いたワークを取り入れることもあります。
たとえば、「人生の地図を描く」「過去の自分に手紙を書く」などの方法です。
それらはすべて、エリクソンが示した「発達は生涯続く」という思想に基づいています。
企業・教育・家庭にも生かせる理論
エリクソンの理論は、カウンセリングに限らず、幅広い領域に応用できます。
1、企業の人材育成:社員の成長段階を理解し、適切なサポートを行う。
2、教育現場:子どもが「今、どの発達課題に向き合っているか」を見立て、寄り添う。
3、家庭関係:親が子どもの「心の段階」を知ることで、必要な愛情や自由を適切に与えられる。
つまり、エリクソンの理論は「人を育てるすべての現場」で活かすことができる実践的心理学なのです。
エリクソン理論を学ぶ意義 ― カウンセラー養成の中で
TKN心理サロンのカウンセラー養成講座では、エリクソン理論を単に「暗記」するのではなく、「体験」として理解していきます。
たとえば——
1、自分自身の各段階を振り返るワーク
2、クライエント事例を発達段階の視点で分析
3、ロールプレイで「未完の課題」に寄り添う練習
こうした学びを通して、カウンセラー自身が「人は常に成長していく存在」であることを実感します。
それは、どんなクライエントにも希望を見出す力につながるのです。
結論:人はいつからでも「成長」できる
エリクソンの発達心理学が伝えている最大のメッセージは――
「人は一生をかけて成長し続ける存在である」ということです。
どの段階でつまずいても、やり直しができる。
そして、そのやり直しを支えるのが、心理カウンセリングの役割です。
TKN心理サロンは、クライエント一人ひとりの「未完の成長」を信じ、共に歩む場所です。
エリクソンの理論を学ぶことは、人の可能性を信じることでもあります。
それは、私たちカウンセラーの原点であり、変わらぬ使命でもあるのです。

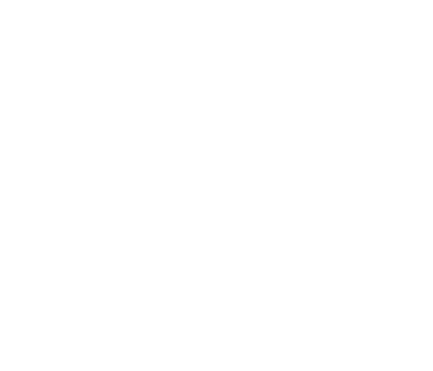 体験講座
体験講座